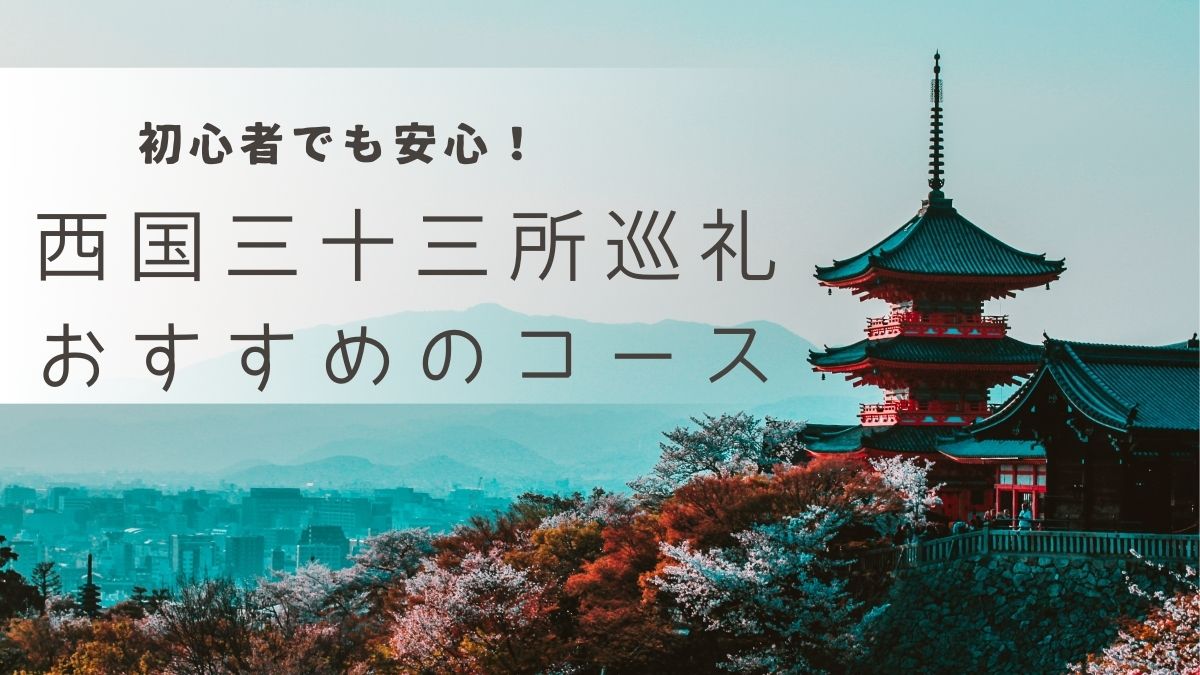「西国三十三所巡礼」は日本最古の巡礼と言われています。
関西地方を中心とした観音霊場を回るものですが、初めての方は次のような不安をお持ちではないですか?
そこで、この記事では初心者の方でもスムーズに西国三十三所巡礼を回るためのおすすめコースや準備するもの、回る時の注意点などをご説明しています。
ぜひ参考にしてくださいね。
西国三十三所とは?初心者でもわかる基礎知識

西国三十三所(さいごくさんじゅうさんしょ)は日本最古の巡礼路で、関西地方を中心にした33か所の観音霊場を巡る旅です。
観音様を祀るお寺を一つひとつ訪れてご縁を結ぶという、心の修行ともいえる体験です。
「三十三」という数には、観音菩薩が人々を救うために変身する三十三の姿を象徴していると言われています。
巡礼は、ただの観光とは違い、自分の心と向き合う大切な時間にもなります。
近年では若い人たちの間でも、パワースポット巡りとして人気が高まっています。
いつから始まったの?歴史をやさしく解説
西国三十三所の歴史は今から約1300年前、奈良時代にさかのぼります。
発案したのは、奈良時代の高僧「徳道上人(とくどうしょうにん)」です。
病気で生死をさまよった際、閻魔大王から「この世で功徳を積むために観音霊場を巡礼しなさい」とのお告げを受けたことがきっかけとされています。
その後、平安時代には花山法皇によって再興され、多くの人々に広まりました。
西国三十三所は、ただのお寺巡りではなく、古くから人々の「救い」や「願い」を込めた特別な旅として続いているのです。
ご利益と巡礼の魅力とは
西国三十三所を巡ることで得られる最大のご利益は「現世利益(げんぜりやく)」、つまりこの世での幸せや願いが叶うこととされています。
厄除け、開運、恋愛成就、健康祈願など、願う内容は人それぞれ。
さらに、心身を清め、精神的な成長を目指す修行の意味合いも持っています。
最近では、御朱印を集める楽しさや、旅の思い出作りとしての魅力も加わり、初心者でも楽しく続けられる巡礼となっています。
実際にお寺を巡ると、自然豊かな風景や、歴史ある建造物、美しい庭園にも心癒されるはずです。
初心者向けの基本ルール

初心者が巡礼を始めるときに知っておきたい基本ルールは、とてもシンプルです。
まず、お寺を訪れたら本堂で手を合わせ、自分の願いごとや感謝の気持ちを伝えましょう。
その後、納経所で御朱印をいただきます。
御朱印はスタンプラリーではなく、参拝の証であり、心を込めて受け取るものです。
また、境内では大きな声で話したり、飲食をしたりするのは控えましょう。
写真撮影も禁止エリアがあるので、事前に確認することが大切です。
こうしたマナーを守ることで、より心豊かな巡礼体験ができるようになります。
三十三所巡り用の御朱印帳(納経帳)もありますよ。
西国三十三所巡礼にかかる時間と費用
西国三十三所を全て回るには、どれくらいの時間が必要なのでしょうか?
移動手段や費用についてご説明します。
全体を回るのに必要な期間の目安
三十三所を回るのに必要な時間(日数)は、巡礼のスタイルによって大きく変わります。
たとえば、休みをまとめて取って一気に回る場合は、だいたい10日~2週間くらいが目安になります。
ただし、現実的には、ほとんどの人が休日や連休を使って少しずつ進めていくスタイルです。
この場合、1年~数年かけて回るのが一般的です。
無理なく自分のペースで
こういった巡礼は、「いつまでに回らなければいけない」といったルールがありません。
無理なく、自分のペースで進められるのが西国巡礼の良いところです。
まずは「今年は近畿圏のお寺を10ヶ所くらい回ろう!」というように、目標を小さく設定すると続けやすいですよ。
移動手段はどうする?電車・車・ツアー比較
移動手段をどうするかも巡礼の計画で大事なポイントです。
電車とバスを使う公共交通機関派は、時間を気にせずにのんびり旅を楽しみたい人におすすめです。
一方で、車移動なら自分のペースで好きな順番にお寺を回れるので、時間を有効に使いたい人にぴったりです。
ツアーの利用もおすすめ
最近では、西国三十三所を回る専用のバスツアーも人気です。
ガイド付きでスムーズに移動できるため、初心者や一人旅の人にも安心感があります。
各移動手段にはメリット・デメリットがあるので、自分の旅のスタイルに合わせて選びましょう。
それぞれの移動手段をまとめてみました。
| 移動手段 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 電車・バス | 運転の心配なし、景色を楽しめる | 待ち時間が発生しやすい |
| 車 | 自由度が高く効率的に回れる | 渋滞や駐車場探しが大変なことも |
| ツアー | 計画不要、楽に多く回れる | 自由度が少ない、日程が決まっている |
宿泊費や食事代はどれくらい?
巡礼にかかる費用は、宿泊場所や食事の内容によっても変わってきます。
たとえば、ビジネスホテルに泊まれば一泊5,000~8,000円程度、温泉旅館に泊まれば10,000円以上かかることもあります。
食事は、地元グルメを楽しむなら一食1,000~2,000円程度を見込んでおきましょう。
宿坊を利用するのもおすすめ
また、お寺の近くには宿坊(お寺に泊まる宿泊施設)がある場合もあり、特別な体験ができるのでおすすめです。
宿坊の場合は、一泊二食付きで7,000~12,000円程度が相場です。
費用を抑えたいなら、早めの予約やキャンペーンを利用するのもポイントです!
御朱印の費用とマナーを知ろう
西国三十三所では、各お寺で御朱印をいただくことができます。
御朱印の費用は、基本的に300円~500円程度です。
33ヶ所すべてを集めると、トータルでおよそ10,000円~15,000円ほどかかる計算になります。
御朱印は「記念スタンプ」ではなく、「お寺に参拝した証」として受け取るものですので、必ずお参りをしてからいただきましょう。
また、御朱印帳を忘れた場合でも、専用の納経帳を購入して始めることができます。
マナーを守って、感謝の気持ちを忘れずにいただきましょう。
お得な交通パスやチケット情報
巡礼にかかる交通費は意外と高額になりがちですが、各鉄道会社や観光協会が発行しているお得な交通パスを利用すれば、かなり節約できます。
また、期間限定で「西国三十三所巡礼特別きっぷ」が販売されることもあります。
こうした情報は、事前にネットや観光案内所で確認しておくと安心です。
少しの工夫で、巡礼旅をもっと快適でお得に楽しめますよ!
初心者におすすめ!効率的なルート紹介
西国三十三所巡礼はどこから回っても構いません。
初心者の方におすすめの効率的なルートをご紹介します。
スタートはここ!京都から巡る王道ルート
西国三十三所巡礼を初めて挑戦するなら、スタート地点は「京都」がおすすめです。
京都は西国三十三所の中でも密集してお寺がある地域で、アクセスも便利。
たとえば「六角堂(頂法寺)」や「清水寺」など、観光名所にもなっている有名なお寺が多く、観光気分も味わいながら巡ることができます。

上の写真は六波羅蜜寺です。
京都市内だけで数か所のお寺を一気に回れるので達成感もあり、最初のモチベーションアップにもぴったりです。
京都は宿泊も便利!
また、京都駅周辺にはホテルも多く、拠点にしやすいのも大きなメリット。
まずは京都から始めて、徐々に周辺地域へと足を伸ばしていくと、無理なく楽しく巡礼を続けられます。
車で一気に回るならこの順番がおすすめ
時間を有効に使いたいなら、レンタカーを借りて車で回るスタイルもおすすめです。
車なら移動時間を短縮できるので、1日に3~5ヶ所巡ることも可能です。
おすすめの順番は、「奈良→和歌山→大阪→兵庫→京都」というルート。
たとえば、奈良の「長谷寺」や「岡寺」からスタートし、和歌山の「粉河寺」「紀三井寺」へ。
その後、大阪の「葛井寺」、兵庫の「中山寺」、そして京都へ戻る流れです。
事前に道路や駐車場情報の確認を!
効率的に巡るためには、高速道路を使う区間も計画に入れておきましょう。
ただし、山間部では道が狭かったり、駐車場が少ないお寺もあるので、事前に駐車場情報を調べておくと安心です。
日帰り&一泊二日で回れるモデルプラン
忙しい人向けに、日帰りや一泊二日で回れるモデルプランもご紹介します!
日帰りプラン
日帰りプランなら、「京都市内のお寺だけを巡る」という設定がベスト。
朝早くに出発して、六角堂、清水寺、今熊野観音寺、革堂行願寺などを巡ると、4~5ヶ所回ることが可能です。
一泊ニ日プラン
【一泊二日プラン】なら、京都市内を回ったあと、大阪の葛井寺や兵庫の中山寺へ足を伸ばすのもおすすめです。
ホテルは京都駅近くに泊まれば、次の日もすぐ移動できて効率的です。
旅のスケジュールは余裕を持って組み、参拝時間や食事休憩も楽しめるようにしましょう。
シーズン別!春・夏・秋・冬の最適プラン
季節によって巡礼の楽しみ方も変わってきます。
- 春:桜が咲く清水寺や長谷寺が特に美しく、巡礼+花見が楽しめます。
- 夏:比較的涼しい高原地帯のお寺を中心に回ると快適です。青岸渡寺は那智の滝の近くで涼しいですよ。
- 秋:紅葉シーズンで、特に三室戸寺や石山寺の紅葉は圧巻。
- 冬:雪化粧したお寺は神秘的で特別な雰囲気を味わえます。
季節ごとのおすすめスポットをリストアップしておけば、何度巡っても新しい発見があるはずです。
こちらは那智の滝です。

雄大な滝は迫力があり、夏でも涼しいですよ。

同じく那智大社と青岸渡寺の桜です。
どの季節に行っても楽しめますよ。
西国三十三所巡礼の持ち物と服装
西国三十三所巡礼では服装の決まりはありません。
四国のお遍路(四国の八十八ヶ所)では「同行二人」と書かれた菅笠(すげがさ)や金剛杖(こんごうづえ)、輪袈裟(わげさ)を持つスタイルをよく見かけます。
しかし、西国三十三所巡礼ではそこまで厳密なルールはありません。
歩きやすい靴や動きやすい服装で大丈夫です。
歩くのに不安がある方は、金剛杖を使ってもいいでしょう。
西国三十三所巡礼に必要な持ち物

次のものを忘れないように持って行きましょう。
- 御朱印帳(または納経帳)
- 小銭(お賽銭や御朱印代)
- 納札(おさめふだ)(事前にネットで購入しておくとスムーズに参拝できます)
- 数珠(特に宗派は問いません。なくても構いません)
- お線香とローソク(寺院で売っていますが、持参してもOK)
- スマホ(地図アプリを見るため)
- 折りたたみ傘
- 日傘または帽子(夏の場合)
- ハンカチまたはウエットティッシュ
- 飲み物
これらをリュックに入れておくと、動きやすいです。
納め札とは

ちなみに納め札とは、上の画像のものです。
自分の名前や住所、祈願する内容などを書いて、寺院に納めます。
札所で買うこともできますが、ネットでも販売しています。
50枚入りで100円~200円程度です。

事前に準備しておくと、参拝時にスムーズですよ。
自分に合った巡礼スタイルを見つけよう
西国三十三所巡礼には、「ゆったり楽しむ派」と「一気に制覇する派」の2つのスタイルがあります。
どちらが正解ということはなく、自分に合ったペースで進めるのが一番です。
ゆったり温泉や風景を楽しみながら回るスタイル
ゆったり派は、1日数ヶ所ずつ回りながら観光やご当地グルメも楽しむスタイルです。
季節ごとの景色や各地の温泉を満喫できるメリットがあります。
一気に制覇するスタイル
一気に制覇派は、まとまった休みを使って短期間で全てを回るチャレンジ型です。
達成感や充実感は大きいですが、体力や移動手段の計画が重要です。
どちらも魅力があるので、自分のライフスタイルや目的に合わせて選びましょう。
失敗しないための注意点
巡礼中によくある失敗は、寺院の受け付け時間が終了してしまうというものです。
道路の渋滞や移動時間を読み間違えて閉門時間に間に合わなかったということがあるので、気をつけましょう。
出発前にお寺の開門・閉門時間をしっかり確認し、1日の訪問先を無理なく設定することが大切です。
また、天気予報をチェックして、急な雷雨や暴風などは避けることが大切です。
無理をせず、天候や体調を見ながら楽しんでくださいね。
次は四国八十八ヶ所へ?ステップアップのすすめ
西国三十三所を巡り終えたら、次なるチャレンジとして「四国八十八ヶ所巡礼」もおすすめです。
こちらは全長約1,400kmにも及び、より本格的な巡礼旅になります。
西国三十三所を通して巡礼の楽しさや達成感を知った人なら、きっと四国巡礼にもワクワクできるはずです。
もちろん、八十八ヶ所をすべて歩く「お遍路スタイル」に挑戦しなくても、バスツアーや区切り打ち(数回に分けて巡る方法)でもOK。
巡礼の旅は、あなたの人生をより豊かにしてくれる素晴らしい体験になりますよ。
まとめ
この記事では、初心者が西国三十三所巡礼をする際のおすすめのコースや持ち物、注意点などをご紹介しました。
西国三十三所巡礼は、初心者でも気軽に始められる、日本ならではの素晴らしい旅です。
効率よく巡るコツは、スタート地点を工夫したり、移動手段を上手に選んだりすること。
そして、自分に合ったペースで、無理なく続けることが大切です。
御朱印帳を持って旅をすると、目に見える思い出も増え、心に残る巡礼体験ができます。
春夏秋冬、それぞれの季節ならではの美しさを感じながら、心をリフレッシュし、願いを込めた旅をぜひ楽しんでください。
小さな一歩から始める巡礼の旅が、きっとあなたに素敵な気づきやご縁を運んでくれるでしょう。